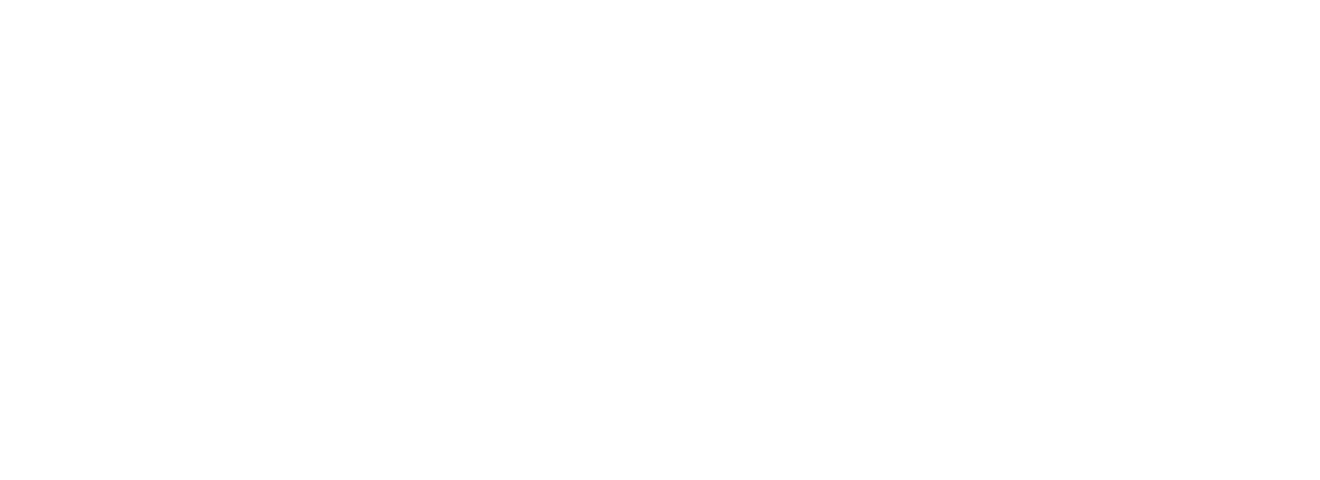
PERCブログBlog
TCAP EMの光学校正試験
少し前の話になりますが,DESTINY+探査機に搭載予定のカメラ「TCAP」のエンジニアリングモデル(EM)(※1)の光学校正試験を行いました.
※1.実際に打ち上げるモデルではなく,地上で試験するためのモデル.
DESTINY+はJAXAが主導し,2028年度に打ち上げ予定の探査機です.ふたご座流星群の母天体(※2)である小惑星フェートンをフライバイ探査(※3)します.千葉工大は搭載カメラ TCAP と MCAP の開発を担当しており,これらを使った観測によりフェートンの素性を明らかにします.フェートンのフライバイは相対速度36km/秒,最大角速度4°/秒という超高速で行われます.探査機の姿勢制御だけでは天体を追い続けられないので,TCAPには「駆動鏡」という仕組みがあり,鏡を回転させて小惑星を追尾しながら撮影できます.もし4°/秒での追尾撮像に成功すれば,この規模の探査機では世界初の成果です.
※2.流星群のもとになる塵を放出する小天体.
※3.探査機が天体に接近して通り過ぎながら観測する方法.
最初にカメラから出力される画像データは数値の並びにすぎません.それを「明るさ」など意味のある物理量を持つ画像に変換する作業を光学校正と呼びます.今回のTCAP EMを用いた試験は,実際に打ち上げるフライトモデル(FM)の試験のリハーサルであり,測定装置や測定方法の確認が主な目的ですが,同時にEM自体の性能確認も行いました.試験はJAXA筑波宇宙センターの「硫酸バリウム積分球」を用いて実施しました.この装置は開口部の分光放射輝度(※4)が保証されており, 空間的に均一な光を出します.開口部をTCAPで撮影することで,TCAPの出力と撮影対象の実際の明るさとの対応を確認できます.試験では露光時間を変えながら撮影し,さらに光を遮って取得する「ダーク画像」も取得しました.積分球が安定するのには時間がかかり,頻繁にON/OFFすることはできないため,TCAPをやぐらで囲って光を遮断してダーク撮像を行いました.また,駆動鏡の回転位置を変えた状態でもデータを取りました.結果として,測定方法・TCAP性能ともに大きな問題はなく,FM試験に向けて良い準備となりました.
※4.波長ごとの光の強さを表す物理量.

やぐらの中に設置したTCAPのエンジニアリングモデル

積分球
試験終了後,つくば駅周辺で夕食をとりました.時刻はすでに夜10時で,多くのお店は閉まっていましたが,幸いにも某イタリアンレストランが開いていました.今回の試験の主担当者である岡本さんは,前回(※5)に引き続き,今回も驚くほどの食欲を見せてくれました.ミラノ風ドリア,ライス(大),フォカッチャ,コーンスープ,ミックスグリルをたいらげた後,デザート代わりにマルゲリータピザまで追加注文しました.研究以上に「食」でも大活躍でした.

大量発注

デザートのピザ
(石橋 高)

