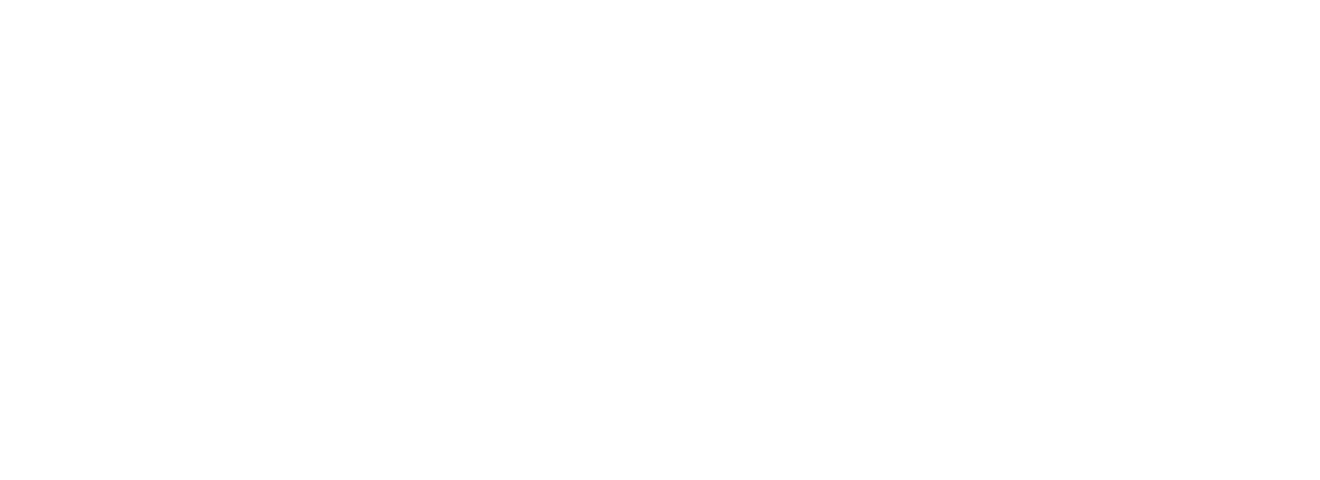上席研究員 兼 天文学研究センター上席研究員
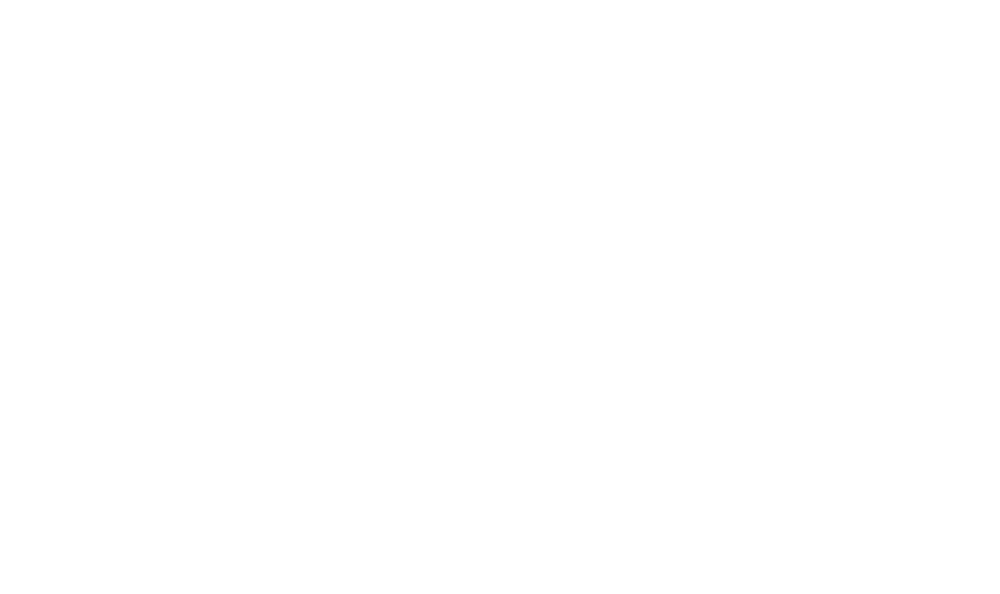
秋田谷 洋Hiroshi AKITAYA
青森県青森市生まれ。東北大学宇宙地球物理学科天文学コース卒業、東北大学大学院理学研究科天文学専攻博士課程修了。博士(理学)。
専門分野は光・赤外線観測天文学。特に、天体が発する光の「偏光」に着目した、星形成過程とその原料となるガス・ダストの性質・運動の観測研究を進めてきた。また、重力波現象に対応した電磁波対応天体の探査・追跡や、超新星、γ線バースト、活動銀河核などの時間変動天体全般の観測研究にも携わる。
観測に用いる装置や望遠鏡の開発と運用にも精力的に取り組んできた。これまでに開発・運用において主要な役割を果たした観測装置として、「偏光分光測光装置HBS(Kawabata+99)」(国立天文台堂平観測所91cm望遠鏡、岡山天体物理観測所91cm望遠鏡、188cm望遠鏡で運用))、「線スペクトル偏光分光装置(Ikeda+03)」(マウナケア天文台ハワイ大学2.2m望遠鏡で運用)、「三波長同時偏光撮像装置MuSaSHI(Oasa+20)」(埼玉大学55cmSaCRA望遠で運用)、「可視赤外線同時カメラHONIR(Akitaya+14)」(広島大学1.5mかなた望遠鏡で運用)等がある。現在建設が進められている口径30m望遠鏡Thirty Meter Telescope (TMT)においても、計画初期段階で主鏡製造技術検討に携わるなど、要素技術開発に貢献した。現在は、千葉工業大学惑星探査研究センター独自の観測装置として、近紫外線観測装置の開発を進めている。